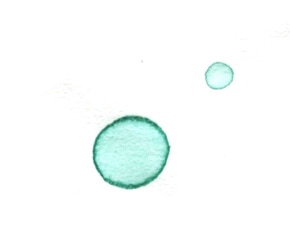Journal
「その人らしく、生きる・死ぬ」ってどういうこと? 映画『30(さんまる)』上映会と対話のワークショップレポート
- Writing
- Emiko Hida
- Photo
- Sayaka Mochizuki

「これからの福祉、医療、葬祭って?」
「その人らしく、生きる、死ぬってどういうことなんだろう?」
「社会課題がたくさんある日本、今後どうなっていくの?」
2025年10月8日、一般社団法人グリーフケア協会、株式会社キュア・エッセンス、株式会社meguriは、映画コミュニティムービー『30(さんまる)』の上映と対話を通して、これらの問いに対するヒントを模索する場を開きました。
ゲストにお迎えしたのは、『30』監督の鈴木七沖さんと、映画の舞台となった多世代型介護付きシェアハウス「はっぴーの家ろっけん」代表の首藤義敬さん。映画に込めた想いやはっぴーの家が大事にしていることを教えていただき、意見を交換しました。その様子をレポートします。

その人らしい最期を迎えるために何ができるだろう。はっぴーの家流の送り出し方
会場は京都の『TRAFFFIC』。主催3社がお声掛けした方を中心に、お集まりいただきました。まずはイベントの主旨について、株式会社オレンジライフ 代表取締役社長の上野山栄作さんからご挨拶。
「今日のテーマは『その人らしく、生きる・死ぬ』です。私は和歌山で葬儀の仕事をしているのですが、こういう仕事をしていると『人は最期どんなふうに送ってもらうと幸せなんだろう』とよく考えます。そうすると、『どんな生き方をしたらいいだろう』という問いに発展するんですね。そして、充実して生きていくにはやっぱり、人と人のつながりが、どんな人と一緒に生きていくかが大事なのだと思います。
この場には医療・介護関係の方、お寺や葬祭業の方、まちづくりに携わる方など、さまざまな方が集まっています。ぜひ普段とは違った横のつながりを築きながら、『その人らしく、生きる・死ぬ』ことについて考えていただけると幸いです」
アイスブレイクとして、参加者同士2人1組になり、自己紹介と共に「お互いの共通項を探す」ワークをしてもらいました。あちこちで話が盛り上がり、予定時間を過ぎて終了を呼びかけてもなかなか止まりません。場が温まったところで、『30』監督の鈴木七沖さんに上映前のスピーチをしていただきました。
「編集者の鈴木七沖と申します。本を作ることをメインの仕事にしていますが、2011年から映像の力で場をつくるプロジェクトを始めました。今からみなさんに観ていただく映画『30』は4作目になります。神戸市長田区で生きる30代の活動を追いかけた作品であり、“あなたがいて、わたしがいて、みんなになる”という三重奏をテーマにしています。そんなことも念頭に置きながら観ていただけると嬉しいです。どうぞお楽しみください」
神戸市長田区にある「多世代型介護付きシェアハウス はっぴーの家ろっけん」。要介護の高齢者を中心に、赤ちゃんや幼児、小中学生の子どもたち、看護師やヘルパー、外国人のダンサー、絵描き、シングルマザー、生きづらさを感じている若者など、多種多様な人たちが毎日ごちゃ混ぜに集まっています。運営するのは30代の若者たち。シェアハウスだけでなく、空き家再生や不動産業も営んでいます。「カオスクリエーター」を名乗る代表の首藤義敬さんが掲げているキャッチコピーが秀逸なのです。
「遠くのシンセキより近くのタニン」
「1人のプロより100人の素人」
「違和感は3つ以上重なるとどうでもよくなる」
「日常の登場人物を増やす」
どれもがシンプルかつあたりまでありながら、なんだかとても新しい……。
ちょっと変わった「30代」が産み出す、世界を少しだけ面白くする方法によって、少しだけ未来が変わっていくかもしれません。(――映画『30』公式サイトより抜粋)

映画には、余命宣告を受けた入居者の“ぱっちん”こと合田貞さんを送り出す様子が記録されています。最期の時間をぱっちんらしく過ごせるようみんなで話し合い、大好きなお酒を楽しめるよう「キャバレーナイト」を企画したり、いよいよお別れが近づいたときはベッドの周りで音楽を奏で語り合ったり。お葬式では生前収録されたぱっちんの掛け声に合わせ、大勢の人が万歳三唱していました。

「いろんな人を巻き込んで、手間をかけて一人の人を見送る。そうすることで、その人が生きた証や時間が心に刻まれる。本来は、こうした故人の生き方が反映されたお葬式を私たちが提案するべきなんですよね」――映画の中で大本山須磨寺副住職の小池陽人さんが語っていた言葉が印象的で、参加者のみなさんも真剣な表情でスクリーンを眺めていました。

居心地の良い空間にするために、だらしなさをデザインする
上映後は、監督の鈴木七沖さん、「はっぴーの家ろっけん」代表の首藤義敬さんに対する質疑応答の時間を取りました。内容の一部を抜粋して紹介します。
参加者「映画の中で、入居者の方の夢を叶えるために六甲山に登って夜景を眺めていましたよね。こういった取り組みには時間や労力もかなり必要かと思います。はっぴーの家には有給スタッフや日常的に関わる人などいろいろな人が関わっていらっしゃるようですが、どのように施設を回しているのでしょうか」

首藤「不思議に思うかもしれないけど、何かやるときに、誰がスタッフで誰がスタッフじゃないかって誰もよくわかってないんですよ。『この日におじいちゃんおばあちゃんと海に行きます』と言うと、常連さんが『自分も一緒に行きたい』と言ったり、スタッフが『子どもを連れて参加しようかな』と言ったり、いろんな人から手が挙がる。ここでは仕事と暮らしの境界線はかなり曖昧で、スタッフが休みの日なのにいることもめずらしくありません。それは、みんなが『はっぴーの家に来ると、お金を払っても体験できないこと、大事なことを学べる』と考えているからじゃないかと思います」
鈴木「ひとつ補足すると、入居者のおじいちゃんおばあちゃんって、スタッフのご両親だったり、知り合いの知り合いだったりするんですよ。前提のストーリーがあって、その上でごちゃっと混ざり合っているんです。
僕が3年間はっぴーの家に通って感じてきたのが、誰もお互いを理解しようとしていないこと。おじいちゃんおばあちゃんが喧嘩していても子どもたちははしゃいでゲームをしているし、その横で女子高生はごはんを食べていて、向こうでは合唱をしていて、こっちではどこの国の人かわからない人がパソコンをいじっている。お互いに理解しようとしていなくて、でもそこにいることは認め合っているんです。そういう場の力ってすごくあると思います」
首藤「子どもの話をすると、はっぴーの家がある長田は、リアルに子ども食堂をやらなあかん地域なんです。でも、だからこそ『子ども食堂』と掲げると絶対に来ない。だからふわっと大人の喫茶のような場所をつくって、子どもがふわっとまぎれ込めるようにしているんです。そんなふうに環境を設計しています」

鈴木「そもそもはっぴーの家という看板もかかっていませんよね。普通の老人ホームと違って、鍵も入り口以外にはかかっていない。だから、誰なのかよくわからない人がリビングでくつろいでいたりします」
首藤「看板の話をすると、だって家ですから。自分が住んでいるところにはっぴーの家って看板が掲げられていたら嫌じゃないですか(笑)。
そして、この後たぶん『いろんな人が来ると大変じゃないですか?』という質問が来ると思うので先に答えてしまうと、大変です。でも、はっぴーの家は不特定多数が出入りする場所ではないんですよ。真っ当な神経していたら、看板がない建物にいきなり入ってこないでしょう。来ているということは、誰かの知り合いか、この場所にめちゃくちゃ興味があるか、どちらかです。“不特定多数”ではなくて、“特定超多数”なんです。だから、知らない人がいても心理的安全性が高いんですね」

参加者「大学でランドスケープデザインを学んでいます。はっぴーの家はカオスだけど自然な状態になっているところがすごいなと思ったのですが、そのために意識されていることはありますか?」
首藤「子どもや若者や高齢者など同質ではない人たちが集まると、最初はバラバラで馴染まないし、お互いに居心地悪く感じる場面もあります。そのほぐし方は、DJの感覚に近いと思います。いまどんな音楽が鳴っているのかよく聞いて、ちょっと違う音を加えてみる。そんなふうにさりげなく配置を変えたり会話をデザインしたりして、気づけばみんなが居心地良く感じるように工夫しているんです。
また、ハードでいうと、僕がつくる空間には、無駄に、邪魔なくらいソファを置きまくっています。そうすると人は自然とそこに座るし、座ると会話が生まれやすくなる。そして、ソファって誰もがちょっとだらしなくなるんですよね。これが大事なことです。
はっぴーの家で大事にしているのは、コミュニティを育むことと、認知症の患者さんの行動レベルを増やすこと。そういった目的を考えたら、あんまり空間が整然としていない方がいいんです。看護師さん・介護士さんって片付けすぎる傾向があって、僕はよく「やめてください、僕はだらしなさのデザインをしているんです」と言っています(笑)。生活感を出した方が、人はくつろぎやすくなるんですよ」
うまくいっている場所には、その場所特有の哲学や人格がある

参加者「カオスな状況では、物事を判断する軸が見出しにくいのではないかと思います。はっぴーの家ではどんなふうに物事を決めていますか?」
鈴木「映画の中で『深めていくから広がっていく』という言葉が出てきたと思います。多くの人は外に外に広げようとしていくけど、彼は目の前のことひとつひとつを深めていって、その結果として広がっていくんですね。いまはっぴーの家にはスタッフが100人くらいいるけど、みんなが自由に動きつつ統制が取れているのは、根っこの部分でつながっているから。そうなるよう、彼が深いところでセッティングしているんですよ」
首藤「僕たちがやっていることって複雑なように見えて実はシンプルで、“出会った人の暮らしのコンセプトを一緒につくる”ことをずっとやっているんです。はっぴーの家に相談に来る人は大抵何かうまくいかないことを抱えていて、そういうときって自分のことしか見えていないものです。一点に集中しすぎて本質が見えなくなる。そこにいろんな人が関わっていろんな要素が重なることで、視野が広がってシンプルにものが見えるようになるんですね。それが混ざり合うことのおもしろさだなと思います。
そのなかで僕が意識しているのは、決めすぎないこと。いつも、『いまこの瞬間、押さえなきゃいけない3割は何だろう』と問いかけて、その3割を守っています。3割きっちりで、7割余白を残す。日々のケアにおいても、誰かを送り出すときも、そんなふうに物事を決めていますね」

鈴木「入社して半年くらいで一度悩むスタッフが結構いますよね。はっぴーの家には決め事もないし『これをしてくれ』という指示もないので、誰かの指示に従って動くのが得意な人には苦痛なんじゃないかな。でも、そのカオスに慣れると居心地が良くなってくる。映画の中で義さんは『違和感も3つ集まればどうでもよくなる』と言っていますが、このどうでもよくなるというのは、テキトーという意味ではなくて、それが余白になっていくということなんだと思います」
首藤「そう、どうでもよくなった瞬間に、ほんまに大事なことが見えてくる。人間ってチームで何かをやりだすと解かなくてもいい問題を解こうとしはじめるし、何かの目的があって始めたことがうまくいくと、手段だったはずのものを目的化しちゃうんですよ。なんのために始めたことなのか、本筋を忘れてしまう。だから、僕は何かがうまく回りはじめたらあえて問題を起こすようにしています。そうすると、『私たちが大事にしたいことってなんだっけ』と考えてくれるから」
鈴木「義さんがカオスクリエイターとして出演したTEDxKobeの動画がYouTubeにあるので、それを観ていただくと彼がやっていることの裏側が垣間見えると思います」
参加者「私もシェアハウスに住んでいるのですが、地域との関係性を深めるような活動を始めるときのヒントをいただきたいです」
首藤「自分たちの場所をおもしろくすることだけ考えるとうまくいかないので、『この場所によって、半径15kmがどう変わるのか』という視点を持って、地域の課題を探すといいと思います。ただ、課題を解決するのって難しいですよね。たとえば、認知症を治すことなんてできないでしょう。でも、認知症があっても楽しく生きるためには、と考えれば、できることはある。そういうことを繰り返していると、『この地域にこの場所があってよかった』と思ってもらえる、愛される場所になっていく。
もうひとつ大事なのは、場所の人格を意識すること。うまくいっているコミュニティスペースに共通するのは、その場所特有の哲学や人格があることなんです。キッチンがあるとか、最新の設備があるとか、機能性の部分はさほど重要じゃない。じゃあどうやって人格を醸成するか。最初からガチガチに決めて、ホームページやパンフレットを作ってもあまり人には響きません。場所の人格って、創業メンバーの想いが浸透していって、徐々に形成されていくものだから。
はっぴーの家では、最初の5人はめちゃくちゃ選びました。『この人やったら同じ感覚でいけるな』という人を厳選して、そこに少しずつ足していく。日本人は単純なので朱に交われば赤くなります。初めに世界観をつくりあげてそこに少しずつ足していくと、場の人格がうまく醸成されていくはずです」

誰かの死が、人と人をつなげてくれている
話は尽きませんが、そろそろ時間です。最後に、おふたりからメッセージをいただきました。
鈴木「『30』を通して一番考えたかったのは、『いまの日本はどうなっているんだろう?』ということです。僕は2003年に起きた夕張市の財政破綻をきっかけにこうした活動を始めました。実はあのとき、全国ほとんどの市町村の職員が夕張市に駆けつけたんですよ。なぜかというと、みんな『明日は我が身だ』と思っていたから。その後、2005年から少子化が加速していき、昨年の出生率は68万人でした。参考までに、戦後2年目の出生率は270万人です。
2023年に発足した人口戦略会議では、『地方自治体の4割強が2050年までに消滅する可能性がある』という報告書を発表しています。僕は総務省や国土交通省のサイトをほぼ毎日見ているのですが、間違いなく消滅すると考えています。労働人口が減り、行政が機能しなくなる未来が見えている。さらに、都会では隣に誰が住んでいるのかわからないのが当たり前の状況になっていますよね。なおかつ、他者と比較することでしか自分のことがわからず、自己肯定感が低い人が増えている。映画の前後には、あえて英語でこうした問いかけを入れました。はっぴーの家を通して、こういうことを考えてほしかったんです。
はっぴーの家のような場所を各地につくるには、ベースとなる物語が、根っこが必要です。ここにいらっしゃるみなさんが何かを起こすときはぜひ、いま何が起きていて、何が必要なのかという“そもそも”の部分に立ち返って、そのうえで必要だと思うものを築き上げていただけたらと思います」

首藤「なんで地域の人はこんなにはっぴーの家を応援してくれるんだろう、プロジェクトが増えると普通は揉め事が増えていくのに、なんではっぴーの家は空中分解せずに済んでいるんだろう。そう考えたときに、誰かの死が僕たちをつなげてくれていることに思い至りました。
はっぴーの家にはリストカットをしているような子どもたちもやってくるけど、数ヶ月経つとみんな『死にたい』と言わなくなるんです。はっぴーの家で、人が死んでいく姿を見ることになるから。日常の登場人物が増えて、その人を送り出すプロセスを地域の人と一緒に経験する。思い出を大事にしながら送って、『あのおばあちゃんの最期、よかったよね』とみんなで語り合う。別れがあることの豊かさというか、そういうことが人と人をつなげてくれていると感じています。
今日ここには葬祭関係の方も多くいらっしゃっていますよね。そういう人たちがまちづくりに関わることは、すごく意味のあることだと思います。まちづくりと言うと『いかにこのまちに人を呼び込むか』ばかり考えがちだけど、『このまちでどんな人をどんなふうに送り出したいか』という視点を持つと、プロジェクトに深みが出るのではないでしょうか」

おふたりの話を受けて、改めて参加者同士の対話の時間を設けました。「その人らしく、生きる・死ぬ」とはどういうことなのか、そのためには何が必要なのか。そして、今日感じたことを受け、これからどんな行動を取っていきたいか。やや抽象的なテーマ設定でしたが、参加者のみなさんは自分自身や目の前の人が感じたこと、考えたことに耳を傾ける時間を楽しんでくださったようです。鈴木さん、首藤さん、たくさんのヒントをありがとうございました!