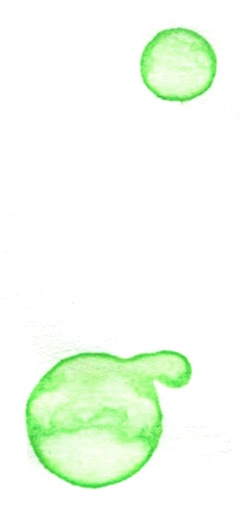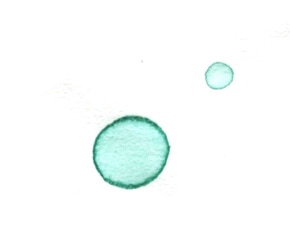Journal

「社員を幸せにする会社」をめざして人財育成に注力する自動車ディーラー・ネッツトヨタ南国。「人間の本質的なモチベーション」を最大限に引き出す環境づくりに取り組み、離職率は2%以下、全国のトヨタ車販売社約260社のうち顧客満足度ナンバーワンを13回獲得するなど高い成果を出しています。
社会・経済システムや価値観の転換期を迎え、多くの企業が変容を迫られているいま、ネッツトヨタ南国の姿勢から学べるものがあるのではないでしょうか。
オムロン フィールドエンジニアリング株式会社、関西電力株式会社、株式会社meguriが企画し、不定期で開催している「エネルギー勉強会」。今回は、2025年2月26日・27日に開催したネッツトヨタ南国視察研修をレポートします。
合理性を求められる会社組織に、新しい価値観を持ち込むために
今回の会場は、高知県高知市にあるネッツトヨタ南国のセミナールーム。エネルギー勉強会主催3社や関係企業の社員を中心に、約30名が集まりました。

まず前に出てきたのは、主催者のひとりである関西電力の熊代知暢さん。今回の視察研修の意図を改めて説明しました。
熊代さん「産業構造や人々の価値観が変わっていくなか、私たちエネルギー業界も新しい価値観をインストールして、社会の中で新しい役割を担っていく必要があります。それは営利を目的とする民間企業にとって必ずしも合理的なものとは限らないという矛盾を抱えているため、それに取り組む合理的な理由を見出す必要があります。その一つとして、人財確保があると思っています。近年、合理だけで自分の仕事を選ばない傾向は増してきていると感じており、 “社員を幸せにすること”を会社の目的として掲げ、人口減少と高齢化が進む高知県で人財を確保し収益を上げつづけているネッツトヨタ南国にヒントがあるのではないかと考え、この研修を企画しました」
続いて、ファシリテーターを務めていただく岩波直樹さん、有冬典子さんから一言。

中央集権型の資本主義社会から自律分散型の共感資本社会への転換をめざす非営利株式会社eumo代表取締役の岩波直樹さん。何度もネッツトヨタ南国を訪れています
岩波さん「この1〜2年、世の中の変化がすさまじいと感じていませんか? 僕らが生きているこの社会は、資本主義という仕組みを使って物質的豊かさを追い求めてきた社会です。それによって人は便利で快適、安心安全な生活を送れるようになりました。ただ、社会システムが強固になるにつれて、人は本質的な問いを忘れ、社会システムを維持することにのみ意識を奪われるようになります。ここに向き合う時代がようやく来たのだと思います。
ネッツトヨタ南国には、“人がシステムに隷属しない考え方・仕組み”が浸透しています。オーストリアの哲学者イヴァン・イリイチが提唱したコンヴィヴィアリティ(自律共生的)な在り方を体現しているのです。この2日間はこれまでの常識を一旦脇に置いて、それが一体どんなものなのか体感していただけると幸いです」

株式会社Corelead /有冬C&Cコンサルティング代表取締役で、「私を生きる あなたと生きる」を理念に内的リーダーシップ開発を行う有冬典子さん。ネッツトヨタ南国を訪問するのは2回目
有冬さん「私は長年、人が自分の“在り方”や“being”を発揮する内的リーダーシップの開発に取り組んできました。ロマンチックな言い方をすると、恐れではなく愛を起点としたリーダーシップです。2010年前後、私の話は会社組織にいる人に全く通じませんでしたが、時代の変化とともに求められるようになってきました。
組織の中にも、愛は必ずあります。それを発揮するには、合理性や恐れのせいで見えていなかった、『本当はこんなふうに働きたい/こんなふうに仲間とつながりたい/こんな社会にしていきたい』という本音に一人ひとりが気づくことが大切です。今日と明日、自分の本当にピュアな願い、根源にある情熱は何なのかに焦点を当てて過ごしていただけたらと思います」
3人の話によって、参加者の姿勢がぐぐっと前のめりになったように見えました。それでは、いよいよ研修スタートです!
「社員を幸せにする会社」とは?――ネッツトヨタ南国相談役・横田英毅さん講演

最初のプログラムは、ネッツトヨタ南国株式会社相談役・横田英毅さんの講演です。
高知県屈指の企業グループである西山グループの創業者一家に生まれ、1980年、37歳のときにネッツトヨタ南国(当時の社名はトヨタビスタ高知)を立ち上げることになった横田さん。「全社員が経営者という組織は強い」「会社の未来を切り拓くのは人だ」という考えから、「社員を幸せにする会社」をめざすようになりました。


社員数が十数名のときから現在まで、採用には毎年1千万円以上の経費をかけているといいます
では、人はどうすれば幸せになれるのでしょうか。横田さんの結論は、「幸せな人生とは生きがいのある人生で、それは仕事を通して実現することができる」というものでした。
「以前製造会社で働いていたときは17時に帰っていましたが、ネッツトヨタ南国を立ち上げてからは連日22時まで会社にいました。でも、私は幸せを感じていたんです。それで、自分と同じような環境、自分で考えて自由に動ける環境をつくったら、社員は働きがいを感じられるかもしれないと仮説を立てました。ここから、“社長室をつくらない”“マニュアルをつくらない”“指示しない”といったネッツトヨタ南国の企業文化が育まれていったのです。また、幸せと満足を区別しなければいけないとも考えるようになりました」。
幸せとは、目的であり必要なもの(=ニーズ)。対して満足とは、目標であり欲しいもの(=ウォンツ)。人は目に見えやすい目標ばかりを追いかけてしまいがちだけど、そうすると目的が遠ざかってしまう。そう横田さんは続けます。
スライド内の黄色で書かれた言葉は「いちばん大切なもの」、ピンクで書かれた言葉は「次に大切なもの」を指しています。「ピンクの内容が大切ではないわけではありません。でも、多くの人はピンクばかり追いかけて黄色を意識していない。そこに問題があるのです」と横田さん
同じことは、働くことについても言えます。求職者の多くは給与や待遇など目に見えやすいものを求めますが、ネッツトヨタ南国は働きがいを追求することが自分たちの価値であり目的と定め、まっすぐにそこに取り組んできたのです。

「いちばん大切なことを見極め、大切にする」。言葉にすると簡単そうに思えますが、実践するのは難しいもの。横田さんはそれを長年実践してきたのだということが伝わってくる講演でした。
採用希望者には、「自分はどういう人間なのか」に徹底的に向き合ってもらう。――従業員クロストーク

次のプログラムは「従業員クロストーク」。採用部門リーダーの小松友紀さん、みらい創造室 室長の森近佳典さんと、参加者とのやりとりの一部をご紹介します。
参加者:どのように社員の価値観を合わせているのか教えてください。
小松さん:採用時の企業説明会などで、ネッツトヨタ南国は私たちらしさを全面に押し出しています。そうすると、9割の学生さんに引かれます(笑)。でも、1割ほど、何かを感じてくれる人が残るんです。そこで私たちらしさに共感・共鳴してくれる人が集まる傾向がありますね。ただ、価値観を合わせているという意識はありません。社内にもさまざまな価値観の人がいますし、それでいいと思っています。
森近さん:3年目には3年目の考え方があるし、10年目には10年目の考え方がある。それが強みにもなるので、揃えてしまうのはもったいないと思っています。後輩に接するときには、自分の考えや価値観を押し付けないように気をつけています。
参加者:社員のみなさんは会社が好きすぎて家庭に支障が出たり、事情があって転職したときにギャップに苦しんだり、ということはないのでしょうか?
森近さん:僕は家族が大好きなので、もし家庭と会社どっちを取るかと言われたら迷わず家庭を取ります(笑)。また、万が一退職することになったとしても、ここで学んだことは次の場所でも必ず活きると思っています。これまで転職された方もそうなんじゃないかな。
小松さん:「家庭か、仕事か」と問われると、「なぜ二者択一で考えるんだろう?」と疑問に感じます。仕事を頑張ること、良き上司として良きリーダーシップを発揮することは、良き母であることとつながっているのではないでしょうか。最近の学生さんはワークライフバランスを重視しますが、その言葉自体に「ワークは我慢して行うもの」という考えが含まれているように感じます。だから私は、「ワークライフインテグレーションという考え方を取り入れてもいいのではないでしょうか。仕事の中に自分を成長させ、豊かにするものがある。私はそれを体感しています」とお話ししています。

参加者:仕事にやりがいを感じるには内発的動機が必要だと思いますが、採用の際、どのようにそれを見極めているのでしょうか。
小松さん:見極めない(笑)!だって、見極められませんから。私たちはとにかく、相手がどういう人間なのかを深く理解することを大事にしています。最終面接では、マネージャー8人と採用担当2人、計10人の面接官が1人の学生に向き合います。そこで大事にしているのは、志望動機ややりたいことではなく、「自分がどういう人間かを自分で語れること」です。
そもそもその前段階で、学生さんには生まれてからこれまでの出来事を振り返ってもらい、何が自分という人間を形作ってきたのかを一緒に分析します。次に2時間半ほどかけて適性検査を行い、「あなたを指標的に見るとこうなります」とフィードバックします。要は、企業を知る前にまず自分を知ってもらうんですね。その上で、「この先どうなっていきたいか」について一緒に話をする。そうやって長時間かけてお付き合いしていくと、学生さん自身が「自分の未来のために、ネッツトヨタ南国で働くべきか」を見極められるようになるんです。

「選考過程で相手の人生と本気で向き合うから、不採用となった学生さんからお礼状が届いたり、数年後にお客さんになってくれたりします」と小松さん
パッションみなぎる小松さんと、落ち着いた口調で話す森近さん。おふたりの話しぶりからも、ネッツトヨタ南国がそれぞれの個性やスタイルを大事にしていることが窺えました。
キーワードは“圧倒的主体性”――ネッツトヨタ南国仕事場見学
クロストークの後は、2班に分かれて仕事場見学へ。案内役を務めてくださったのは、ビスタワークス研の窪田瀬奈さんと、長山大助さんです。
後方の建物は、子育て中の社員が安心して働けるように整備した保育園。社員のみなさんは、「こどもたちにいきいきと働く大人の姿を見せること」を自分たちの使命と考えているそうです。いつか卒園児がネッツトヨタ南国に就職する日が来るかもしれませんね。
クリーニング工場はガラス貼りになっていて、作業風景が外から覗けるようになっています。「この仕事は営業が花形だと思われがちですが、営業がお客様に全力で向き合うことができるのも各部署があってこそ。どの部署で働く方もお客様につながっている、それがわかるような職場環境にしています」と窪田さん。
職場環境をより良くするため、2024年に整備された休憩室。シャワーやロッカーがあり、整備士はここで昼食を食べたり昼寝をしたりとくつろいで休憩することができます。
「実際に走って乗り心地を確かめてほしい」という想いから、車はショールームではなく外に展示。ショールームはスタッフとくつろいで話ができるカフェのような空間になっていました。また、「お客様の様子に気づいてすぐに対応する姿勢」をスタッフに養ってもらうため、扉はあえて自動ドアにせず、トイレのサインもわかりづらくしているといいます。
広々とした整備場。整備士は車に向き合うだけではなくお客様への説明も行い、ときにはキャリア教育にも携わります。また、仕事の割り振りを行う「コントローラー」という役職があり、大きな権限を持っているそう。これらはすべて、横田さんが言っていた「全社員が経営者の意識を持った組織」にするための取り組みです。
「私たちの姿勢に共感して、『車を買うなら/車検をするならネッツトヨタ南国で』と遠方から来てくださる方も多く、一番遠くだと北海道から来てくださっています」と窪田さん
道中、窪田さんは“ショールーム前の歩道に花を植えるプロジェクト”“未就学児向けのお仕事体験プロジェクト”“工業高校生向け職業体験・1分の1プラモデルプロジェクト”などさまざまな社員発プロジェクトについて教えてくれました。ポイントは「やりたい人がやりたいときにやる」こと。毎年予算化するのではなく必要なときに予算をつけ、なんらかの事情で関わることができない人が疎外感を感じないようにすることにも気を配っているといいます。
エネルギー勉強会主催者のひとり、オムロン フィールドエンジニアリングの榎並顕さんが「キーワードは“圧倒的主体性”だな」と感想を漏らすと、ほかの参加者から「たしかに、主体性を奪うものを徹底的に取り除いている」と声が挙がり、その後もさまざまな場面で“圧倒的主体性”という言葉が飛び交いました。
セミナールームに戻り、参加者には忘れないうちに感想をポストイットに書き出してもらいました。その後は横田さんや窪田さんを交え、有志で懇親会へ。高知のおいしい郷土料理に舌鼓を打ち、1日目のプログラムは終了しました。
関係性の質を高めることで、結果がついてくるーー結城貴暁さん講演

「みなさんの会社にとって、人財育成とは何がどうなることですか?」
2日目の朝。ネッツトヨタ南国採用/共育担当・結城貴暁さんの講演「新時代の到来、人が輝く職場を創る〜弱小自動車ディーラーの独自の人財戦略〜」は、そんな問いかけから始まりました。
「どこへ行っても活躍でき、自分も他者も幸せにできる人間を育てることが私たちの使命です」と力強く話す結城さん
結城さん「ネッツトヨタ南国の考える人財育成とは、端的に言うと社員が(生物種としての)ヒトから(社会的存在としての)人間になることです。科学的には、脳の前頭前野が発達していくことが、人間になっていくプロセスだと言われています。前頭前野は人と関わり、さまざまな経験をすることで発達していきます。でも、いまの若者にはそうした経験が足りていません。だから、会社で心が動く体験を積んでもらうのです」
たとえば、ネッツトヨタ南国では入社式の際、親御さんからの手紙を代読することに多くの時間を費やします。それによって新入社員には社会人としての自覚が、先輩社員には「大事なお子さんを預かるんだ」という意識が芽生え、絆が深まるといいます。また、入社後半年間、新入社員はA4ノート1ページにびっしりと日誌を書くことになります。それによって内省する力・考える力が身につき、日誌を確認する先輩社員とのコミュニケーションも生まれるのです。
内容の変化から先輩社員が新入社員の不安や悩みに気づき、相談に乗ったり「失敗してもいいからやってごらん」と声をかけたりすることも少なくないといいます
結城さん「日本人は場に適応する力がずば抜けています。そこから逆に考えると、“主体性がない”など個人の資質に思えるものも、場がそうさせているだけかもしれない。個人攻撃をして終わりにせず、“場を変える”“チームで人を育てる”という意識を持つことが、これからの時代には必要なのではないでしょうか」
関係性をないがしろにして数字ばかりを追い求める職場では、社員は「お客様の役に立ちたい」という気持ちを大事にできず、能動的に動くことができません。すると、他社と差別化できるところは価格だけになり、安売り競争となって業績も伸び悩みます。“結果や行動の質を高めるには、考え方の質、関係性の質を高めることが重要だ”――これが結城さんの考えです。

講義中はさまざまな問いが参加者に投げかけられ、グループごとにお互いの考えを共有する時間がありました
結城さん「ネッツトヨタ南国では、社内外の人と料理をして食卓を囲んだり、お客さんを交えて仮装コンテストをしたりと、さまざまなプロジェクトを行なっています。このとき、社員は部門や役職、世代を超えて協力します。そうすると、“社内にどんな人がいて、誰が何を知っているのか、得意としているのか”をみんなが把握できて、何かあったときお互いに頼り合えるようになるのです。1人の問題解決能力を伸ばすのではなく、みんなの合わせ技で問題解決能力を高める。それがネッツトヨタ南国の方針です」
ネッツトヨタ南国では、「長所を磨き、短所は無理に克服するのではなく仲間と補い合う」ことを大事にしているそう
休憩時間になると、数人の参加者が結城さんを囲み、熱心に意見交換をしていました。人財育成に課題意識を抱えた方にとって、結城さんの話は大きな刺激となったようです。
今回学んだことを自分の組織に活かすには?――振り返りワークショップ

最後のプログラムは、岩波さん・有冬さんによる振り返りワークショップです。感じたことをポストイットに書き出してグループで共有した後、全員に向けて発表してもらいました。

「時間や経験を共有することが大事だと思った」「うちの組織は圧倒的にコミュニケーション量が足りていないことがわかったから、まずはそこに取り組みたい」「自分が熱を持たなければいけない」といった声もあれば、「上の世代はどうしたら変わるのだろうか」「プロジェクトを行う余裕をどうやってつくっているんだろうか」といった声も。みなさん、ネッツトヨタ南国の姿勢に深く感銘を受けた一方で、「じゃあうちの組織にどう取り入れられるだろう」と戸惑いも感じている様子でした。
有冬さん「やることも課題も山積みの毎日のなかで何ができるだろうと戸惑う気持ちはよくわかります。でも、この2日間で感じたことに蓋をしてしまうのはもったいない。私が今回ひしひしと感じたのは、『幸せになるには、面倒くさいことに取り組まないといけない』ということです。ネッツトヨタ南国は、採用から研修まで、そしてその後も、ずっと社員に内省を促しています。『自分の本当の幸せとは何か』という面倒な問いに向き合わせている。そうしないと、人はすぐに便利さや満足に絡めとられ、より深い喜びを与えてくれる幸せを手放してしまうんですよね。みなさんもこの機会にぜひ、自分が本当は何を大切にしたいのかを掘り下げて言語化していただきたいです」
岩波さん「自分の目の前に広がる世界は、自分の価値観を反映しています。ディーラーって、普通は値下げ合戦になるじゃないですか。でも、それは売る人が普段から損得勘定で世の中を見ていて、『少しでも安いほうがいい』という価値観を持っているからです。ネッツトヨタ南国は違います。人が幸せに生きることがいちばん大切だと思っていて、それを価値として提供しているから、本当の豊かさに気づける人がお客さんとして集まってくる。だから、僕たちはまずやるべきなのは、自分の持っている価値観、思考の枠組みを見直すことです」
有冬さん「もし、『どうせ、うちでは無理だな』と羨ましさや失望などを感じたら、ぜひその感情の奥にある本音まで掘り下げてみてほしいのです。そこには、みなさんが『本当は大切にしたい(かった)もの』が隠れているかもしれない。そして、感じたことを同じ部署の人に話してみる。全員に伝えるのは無理でも、1人に伝えることならできるのではないでしょうか。意外と、『実は私もそれを大事にしたいと思っていた』という声が返ってきて、少しずつ広がっていくかもしれません。そうやって、一年後に何割かでも変わっていたらいいですよね」
岩波さん「僕たちは物事を二項対立で捉えがちだけど、二項動態で考えることが重要です。二項動態とは、矛盾する対立項が相互作用する状態のこと。どっちが正しいではなく、動きながら、比率を変えながら、どっちも取りに行くということです。ネッツトヨタ南国では、“みんなが幸せに生きること”と“業績を上げること”が対立していませんよね。両立は可能なんです。ただ、そのためには論理だけではなく感性が必要です。『やらなくちゃいけない』じゃなくて、『やっていきたいよね』と思うことに1歩踏み出してほしい。
いきなり全部変えるのは無理ですよ。だから、自分の仕事のやり方を少し変えてみる。こういうところに自分のチームメンバーを連れてきて共体験する。その輪を広げていく。『あいつらは何にもわかってない』みたいな対立概念に陥らないよう気をつけながら、小さな一歩を積み重ねてください」


岩波さんが用意してくださったスライドから一部抜粋
2時間にわたり、さまざまな角度から熱意を持って話してくださった岩波さん・有冬さん。最後に、「満足に飲み込まれないように、“幸せの味をしめる”という体験を繰り返してほしい」(有冬さん)「自律共生的な組織を実現するにあたり、個人的な喜びと社会的な喜びの接点を見つけて、小さくても行動を起こしてほしい」(岩波さん)と参加者へエールを送り、場を締めくくりました。
濃厚だった2日間もこれにて終了。参加者のみなさんは自分の組織に何を持ち帰り、どんな一歩を踏み出すのでしょうか。それによってどんな変化が生まれたか、ぜひ今後のエネルギー勉強会で共有いただけると幸いです!