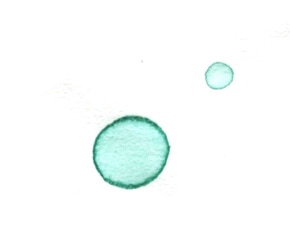Journal

2011年に発生した福島第一原子力発電所事故。周辺住民約16万人 に避難を強いる大きな被害をもたらし、原子力エネルギー利用における安全対策の重要性を改めて認識させる契機となりました。
あのとき現場にいた人はどんな体験をしたのでしょうか。そして、廃炉作業や相双地域の復興はどこまで進んでいるのでしょうか。持続可能な社会を実現するためのエネルギー政策の現状と課題を理解するために、原発事故を直視することは避けて通れません。
オムロン フィールドエンジニアリング株式会社、関西電力株式会社、株式会社meguriが企画し、不定期で開催している「エネルギー勉強会」。今回は、福島第一原子力発電所の視察ツアーを行いました。その様子をレポートします 。

福島復興のシンボル・Jヴィレッジの軌跡
2025年5月19日午後。エネルギー勉強会主催3社の社員や再生可能エネルギー事業者の社員など20数名の参加者が、福島県双葉郡楢葉町と広野町にまたがって立地するサッカーナショナルトレーニングセンター・Jヴィレッジのホールに集まりました。
最初のプログラムは「Jヴィレッジの軌跡」。Jヴィレッジホスピタリティ事業部・森恵太さんが、映像資料を交えながらJヴィレッジの誕生から現在までの道のりを語ってくださいました。

1997年、日本初の本格的なナショナルトレーニングセンターとしてオープンしたJヴィレッジ。日本サッカーの重要拠点であり、海外チームも訪れる国際的施設として発展してきました。
しかし、原発事故の後、福島第一原発から20km圏内の境目にあったJヴィレッジは原子力発電所事故対策の収束拠点に指定されます。天然芝ピッチには鉄板が敷き詰められて資材置場や駐車場に。スタジアムにはプレハブ式単身寮や施設が建てられ、雨天練習場は汚染物質の保管場所として使われました。2012年には収束拠点としての役割はほぼ終了しましたが、ピッチの変わり果てた姿を見て、「もう復活はできないのではないか」と考えた職員も多かったといいます。

「そうしたなか、2013年9月に東京オリンピック・パラリンピックの招致が決定し、Jヴィレッジをトレーニングセンターとして再開する計画が立てられたのです。元に戻すだけでなく、一年中常緑で質のいいピッチを維持できるように芝生の管理を変え、全天候型練習場も新たに設置するなど、新生Jヴィレッジとして再開準備が進められました」
2019年の再開と同時に、JR常磐線Jヴィレッジ駅も開業。2021年の東京オリンピック・パラリンピックの聖火リレーはJヴィレッジから始まりました。また、今年11月にはデフリンピックのサッカー競技が開催される予定です。Jヴィレッジは福島復興のシンボルとして、相双地域に賑わいをもたらしています。

森さんのお話の後、参加者は展望ホールへ移動。美しく整備されたピッチを眺めながら、時間を経た変化の大きさを噛みしめました。

福島第一原子力発電所1・2号機当直長・伊沢郁夫氏講演
続いてのプログラムは、震災当日に福島第一原発1・2号機の当直長を務めていた伊沢郁夫さんの講演です。伊沢さんは映画『Fukushima 50』で佐藤浩市が演じた伊崎利夫役のモデルとなった2人のうちの1人で、当時は53歳でした。

2011年3月11日14時46分、三陸沖の海底を震源とするマグニチュード9の地震が発生しました。1号機と2号機の間にある中央制御室にいた伊沢さんは、「これまでの人生で味わったことのない」すさまじい揺れを体験。一抹の不安を覚えたものの、原子炉は設計通り自動的に停止し、ほっと胸を撫で下ろしたといいます。しかし、30分 が過ぎた頃、異変が起きました。地震により一部が壊れた変電所に代わって電力を供給していた非常用ディーゼル発電機4台が停止。さらに、バックアップの直流電源も止まってしまった のです。
「全電源を喪失したことにより、さまざまな計器が次々消え、真っ暗になりました。それまで鳴っていた複数の警報音も、人の声も全てが消えました。誰も声を上げられなかったんです。部下が一斉に私の顔を見たけれど、私も何も言えませんでした」。

なぜこんな事態になっているのか、一体何が起こっているのか。その答えをもたらしたのは、1号機の建屋内へ確認に行っていた運転員でした。「建屋1階に海水が流れてきています」という叫び声と共に、倒れ込むように中央制御室に戻ってきたのです。
「原子炉が自動で止まっても、運転員が現場に行って確認する必要があります。地震の後、部下はすぐに確認に行こうとしましたが、私は『津波が来るかもしれない』と警戒していました。ただ、原子炉建屋1階は海抜10mの場所にあります。まさかそこまで津波が来るはずはないと思い、行かせたんです。建屋の地下にいた彼らは地鳴りの音と浸水に気づいてすぐに階段を駆け上がり、腰まで水に浸かりながら必死に流れに逆らって戻ってきてくれました。……私はもう少しで、自分の部下を失うところでした」。
津波が引いた後も、余震は数分から数十分おきに発生していました。さらに、横転した車や瓦礫が道を阻んでいます。現場の状況はわからず、建物内は真っ暗で、地下は水没している。そんなところにまた部下を送り込んでいいのか。でも、このまま何もせずにいたら、原子炉の状況はどんどん悪くなるーー。伊沢さんは大きな葛藤を抱えながら現場の指揮に当たりつづけました。
「ちょうどその頃、3〜4号機の責任者から、原子炉建屋に向かった若い運転員2人と連絡が取れなくなったと聞いたんです。津波が来たときに地下にいて、連絡が取れなくなった。『あぁ、ダメだ』と思いました。『部下たちを全員無事で家族のもとに帰さなければいけない、それが自分の責任だ』と強く思いました」。

事故が起こっても、格納容器に放射性物質を閉じ込めておけば、外に漏れ出ることはありません。しかしこのとき、格納容器の圧力が急激に高まっていました。破損を防ぐため、内部にたまった気体を外に放出して圧力を下げることをベント操作といいます。3月11日から12日へと日付が変わる頃、発電所敷地内の重要免震棟で全体の指揮をとっていた吉田昌郎所長から伊沢さんの元へ、「1号機のベントをするしかない」という連絡が入りました。
「絞り出すようなその声がいまでも耳に残っています。技術者として、私もベントをするしかないと頭ではわかっていました。でも、自分の生まれ育った故郷に、放射性物質を少なからずばら撒くことになるわけです。『自分は一体これまでこの発電所で何をしてきたんだ』と、悔しさと申し訳なさ、やるせなさが入り混じったような、言いようのない感情を味わいました」。
電気が通っていれば、中央制御室でスイッチを押すだけでベントは可能です。しかし、このときは人間が現場まで行く以外の方法がありませんでした。では、誰が行くのか。その人選は伊沢さんに委ねられました。
「最初は誰も手を挙げず、シーンとしていました。どれだけ被ばくするかわからないし、無事戻ってくることができたとしても後遺症が残るかもしれない。指名なんて、命令なんてできません。だから私は、自分が行くと言いました。しかし、後から駆けつけてくれた運転員、同世代や先輩の職員たちが私を制止して、『俺たちが行く』と言ってくれたんです。その様子を見て、それまで黙っていた若い部下たちが何人も『自分が行く』と手を挙げてくれました。もちろん、ずっと黙っていた人もいます。それは当然のことです」。

ベントは一ヶ所は成功しましたが、もう一ヶ所は失敗。その後、12日午後に1号機が水素爆発しました。中央制御室の建物そのものが壊れたのかと思うほどの衝撃に見舞われ、伊沢さんは「終わった」と思ったといいます。
「水素爆発だったと知ったのはしばらく経ってからです。爆発を受けて運転員全員がここに詰めているのはもう限界だと感じ、交代で免震重要棟に避難することにしました。私自身も事故後初めて免震重要棟に足を踏み入れたのですが、そこには600人を超える職員や関連企業の社員、自衛隊員、消防士などが詰めていました。階段の踊り場や机の下など、あらゆる場所で人が横になったり膝を抱えたりしていて、野戦病院さながらです。でも、私はずっと中央制御室で『部下を守らなければ』という責任者としてのプレッシャーを感じていたので、『こんなに人がいるんだ、まだまだやれるぞ』と心強く感じました。
関連企業にも、福島を地元とする人が大勢働いていました。発電所から社員を退避させる決断をした社長に対し、『残らせてくれ』と直談判した方も多かったと聞いています。彼らがいなかったら、いまの福島第一原発はありません」。

しかし、3月14日午前、3号機が水素爆発。誰もが「次は2号機だ」と恐々とするなか、15日早朝に大きな衝撃音が観測されました。ここで吉田所長は必要最小限の人員を残し、ほとんどのスタッフを福島第二原子力発電所に退避させる決断をします。
「我先にと人を押し退けて走っていった人もいれば、泣きながら出ていった人もいます。これまで押さえ込んでいた恐怖心や、自分の家族や友人を心配する気持ちが一気に溢れたのでしょう。一方で、『お世話になりました』と頭を下げていく人もいましたし、座り込んで『自分は残ります』と言い張った若い運転員もいて、『これは命令だ』と避難させた一幕もありました。残ったのは60数名。最初は誰も声を発さず、『そうか、お前も残ったか』と顔を見合わせていました。
そのときの感情は、それぞれ違ったと思います。私自身は、『自分の命を犠牲にしてでも』といった覚悟があったわけではありません。残ったらこの先どうなるかと考える余裕もありませんでした。ただ、やるべきことがあった。だから残ったんです」。

原発事故発生後数日間の緊迫した状況を語った後、伊沢さんはご自身の考え方の変化も共有してくださいました。
「東京電力に入社してさまざまなことを学び、技術者として安全を確信していました。絶対にありえないような状況まで想定して設計され、訓練もしているのだから、と。しかし、事故は起こり、地域住民のみなさんを避難させる事態になってしまいました。
現在東京電力では、二度と福島第一原発のような事故を起こさないよう、『こんな地震や津波が来たら日本は終わりだ』と思うような状況も想定して物事を進めています。これは当たり前のことです。でも、どんなに高度な技術を使っていても、どんなに安全な設計をしていても、『それによって新たなリスクは生まれないのか』『何か抜けている視点はないのか』と最後の最後まで考えなければいけない。技術者には、そういう姿勢が絶対に必要です。そして、『事故は絶対に起こりません』と豪語するのではなく、一つひとつの選択肢にどんなリスクがあるのかを、一般の方々にきちんと説明しなければならないと考えるようになりました」。

一連の事故対応を終えて避難先に行った後、伊沢さんは「当時の状況を語りたくない」「人に会いたくない」「テレビや新聞を見たくない」と、半ば引きこもりのような状態に陥ったそうです。しかし、家族や親族に支えられ、少しずつ回復していきました。2023年には、意を決して双葉町へ帰還。現在は震災前に仲間と発足した地域住民向け総合型スポーツクラブを再開し、運営に携わっています。
「居住人口が200人にも満たない双葉町ですが、昨年運動会を企画したところ、東京や埼玉など各地の避難先から人が駆けつけてくれて、参加者は200人を超えました。活動を続けることで、1人でも2人でも住民の帰還につながれば。この輪が広がっていくことが私の夢です。そして、福島第一原子力発電所の行末を、一番近くで見守っていきたいと思います」。

講演が終わった後、参加者からは「あのとき現場を守ってくださりありがとうございます」といった感謝の言葉や感想とともに、たくさんの質問が寄せられました。終了予定時刻を過ぎても手が挙がりつづけ、伊沢さんは一つひとつの質問に対し丁寧に、正直に答えてくださいました。
福島第一原子力発電所視察

5月20日朝。参加者を乗せたバスはJヴィレッジを出発し、東京電力廃炉資料館へ。ここで「福島第一原子力発電所の反省と教訓」「ALPS処理水の海洋放出について」といった動画を閲覧した後、専用バスに乗り換えて福島第一原子力発電所に向かいました。

会議室で発電所の概要に関する説明を受け、入退域管理棟でセキュリティチェックを通って構内へ。入構するには、事前にコピーを提出した顔写真付きの本人確認書類の原本が必要です。また、テロ対策のため、カメラやスマホ、バッグなどは持ち込むことができません。一方、防護服やマスクなどは必要なく、私服の長袖長ズボンの上に専用ベストと線量計を身につけるだけで中に入ることができました 。


構内の移動は専用バスで行います。車窓から、ALPS処理水を格納した貯蔵タンクやセシウム吸着装置キュリオンの使用済フィルターを格納したコンクリートボックスが見えました。貯蔵タンクの容量は700トンから1400トン。1000基が大熊町側の敷地に置かれています。コンクリートボックスは、現在双葉町に建設中の個体廃棄物貯蔵庫 が完成したら移設する予定だといいます。

バスは免震重要棟の前を通り、1号機から4号機の前へ。ここで参加者はバスを降り、原子炉建屋を見渡せるブルーデッキに自分の足で進みました。1号機までの距離は100メートルほど。水素爆発により壁や屋根が吹き飛び、骨組みだけになっています。爆発の激しさを物語る光景に、参加者が一瞬息を呑む様子が伝わってきました。

1号機の建屋上部に視線を向けると、いまでも瓦礫が重なっている様子が見てとれます。撤去する際に放射線が付着した埃が飛散する可能性があるため、大型カバーを設置してから瓦礫を撤去し、2027年から2028年に使用済燃料を取り出す計画を立てているとのこと。1号機の燃料プールに残された使用済み燃料の数は392体。カバーの設置は今年の夏を予定しているため、現在のように剥き出しの状態が見られるのはあと少しのようです。

2号機は1号機の水素爆発の衝撃により建屋側面のパネルが開き、水素が外に出たことで爆発を免れたと言われています 。2号機の燃料プールに残された使用済燃料の数は615体。2025年度末に取り出しが計画されています。


1号機と同じく水素爆発した3号機・4号機はそれぞれ2021年・2014年に使用済燃料の取り出しを完了しています。ただし、1号機・2号機・3号機には、高温となった核燃料が溶けて周辺の金属材料などと一緒に冷えて固まった「燃料デブリ」が残されています。2024年9月から11月にかけ、事故後初めて燃料デブリの試験的取り出しが行われました。現在、日本原子力研究開発機構が取り出した燃料デブリの調査をしているといいます。

なお、入退域管理棟周辺の放射線量は1.1μSv/hほどでしたが、ブルーデッキの線量計は46.5μSv/hという数字を表示していました。

再びバスに乗り、5号機・6号機のグリーンデッキ前で降車。デッキから海側に目を向けると、白い波が寄せては引く穏やかな光景が広がっていました。その様子だけ見ていると、ここで日本を揺るがす事故が起き、いまも廃炉作業が続いているということが信じられません。人間以外の生き物は、事故による環境の変化をどのように受け止めているのでしょうか。

入退域管理棟に戻り、処理水について改めて説明を受けました。
1〜3号機では燃料デブリを安定させるため、常に水を循環させて冷却しています。この燃料デブリに触れた水と建屋に流れ込んだ地下水が混ざることで汚染水が発生します。雨水の土壌浸透を抑える敷地舗装や凍土方式遮水壁の設置、地下水汲み上げといった対策により、2014年度に1日540立法メートル発生していた汚染水は、2022年度には1日90立法メートルまで減っているとのこと。
発生した汚染水はセシウム吸着装置や淡水化装置、多核種除去設備(ALPS)などを通り、放射性物質の大部分が除去されたALPS処理水となります。ALPS処理水の貯蔵タンクは1000基を超えており、災害発生時に倒壊のリスクがあることなどからタンクの処分が議論されてきました。6年以上にわたる議論の結果、処分方法を海洋放出とする方針が決定。2023年8月から2025年5月現在までに、11回の海洋放出が行われています。

最後に、放射性物質汚染検査ゲートを通り、専用ベストと個人線量計を返却しました。線量計の数値は0.01μSv/h。レントゲン写真を一枚撮った程度の被爆量でした。
2日間を振り返り、エネルギーの未来を考える
視察後、富岡生涯学習館「学びの森」へ移動して昼食を取り、振り返りを行いました。株式会社フューチャーセッションズ・坂本悠樹さんのファシリテーションのもと、まずは4〜5人のグループを複数作り、次に2つの円を作って対話。最後に1つの大きな円を描いて、それぞれのグループで語られたことを共有しました。その内容を少しだけ抜粋します。

「今回のツアーを通して、過酷な現場から逃げずに踏みとどまってくださった方々、現在も廃炉作業に向き合ってくださっている方々への感謝を強く感じました。電力に限らず、この社会はいろんな人に支えられて成り立っていることを忘れてはいけませんね。一方で、自然はコントロールできるものではないし、人のやることなのでミスもするかもしれない。そうしたリスクにどう向き合っていくのか、考えつづけなければいけないと思いました」。
「慣れというのは本当に怖くて、便利な世の中ができあがるとそれがどうやって維持されているかを忘れてしまいがちですし、2011年にあれだけ怖い想いをしたのに、14年が経って廃炉の状況をまったく気にせず日常を送っていたことに気づきました。廃炉作業は今後数十年続きます。そうすると、原発事故を経験していない人たちが引き継ぐことになる。ちゃんと人を育成していくことができるのだろうかと心配になりました。エネルギーの問題についてみんながもっと知るべきだし、学校教育にも取り入れる必要があるのではないでしょうか」。
「持続可能な社会を考えるなら、消費者の立場から利便性を追求することにどこかでストップをかけなければいけません。でも、これまでの技術革新の歴史の中で、人が便利なものを拒否できたことなんてないんですよね。いまさらスマホを捨ててガラケーで我慢しようなんて言っても、受け入れる人はほとんどいないのではないでしょうか。ただ、その裏側にどんなリスクがあるのか、ちゃんと認識する必要があると改めて感じました。こうして現場に来ること、対話を重ねることが重要なのだと思います」。

「エネルギー問題は本当に難しいと思います。海岸線沿いにあんなに巨大な施設をたくさん作って、自然を破壊して、事故を起こして、それでも原発がなければ日本はここまで成長することはできなかったし、いまの便利な社会も維持できません。さらに最近はAIの普及による電力消費の急増や脱炭素化の加速により、原子力は再評価されてきています。次世代の原子力はかなり安全と言われていますが、それを導入するかどうかは、原子力事業者だけでなく、国全体で議論しなければいけないことではないでしょうか。今回感じたことを、家庭や地域、会社に持ち帰って共有していきたいですね」。

2日間同じ体験をしても、感じたこと、考えたことは人それぞれ異なります。ほかの方の意見に共感して頷いたりはっとしたりしている方もいれば、眉間に皺を寄せ考え込んでいるような様子の方もいました。
エネルギー問題に、誰もが納得できる解はないのかもしれません。それでも、異なる意見に耳を傾け、自分の考えを共有し、議論を深めていくことが大切なのではないでしょうか。
エネルギー勉強会では、今後もさまざまな角度から、私たちの社会とエネルギーの未来を模索する場を作っていきたいと思います。