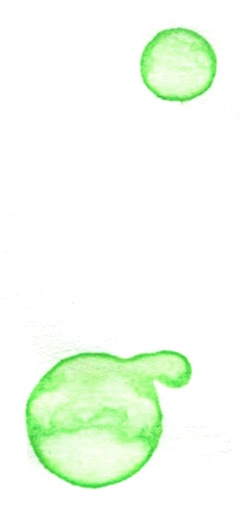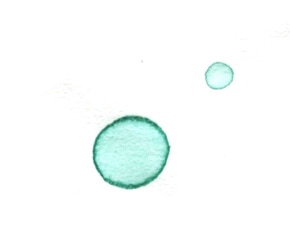Journal

こちらの記事はCQ note記事の原文転載となります
元記事:エネルギー問題はなぜ複雑なのか?「エネルギーをめぐる旅」著者・古舘恒介が語る「エネルギー大量消費社会」が生まれた理由【勉強会レポート】
私たちは産業革命以降、エネルギーを大量に消費することで、かつてない豊かさと利便性を手に入れてきました。
しかし、その代償として気候変動をはじめとする環境問題が深刻化し、社会の持続可能性が問われる時代を迎えています。
そんなエネルギー問題の解決には、技術革新の追求だけでなく、私たちの生き方そのものを問い直す必要があるのではないでしょうか。
その手がかりを探るため、「エネルギーをめぐる旅―文明の歴史と私たちの未来」の著者・古舘恒介氏をお招きし、人類とエネルギーの関係史から現代社会の課題を考察する勉強会を2024年10月4日に開催。
さまざまな企業から参加したみなさまとともに、これからの時代における新しい豊かさのかたちについて対話を重ねました。
本記事では、前半では私たちがエネルギー問題に向き合うために必要な基本的な背景知識と姿勢について、後編では産業革命以降の人類社会の構造と、現代のエネルギー消費、そして参加者同士で行われたワークショップの様子をレポートします。
テクノロジーの進化、人々の考え方や生き方、価値観の変化、温暖化をはじめとする様々な社会課題など、時代の変化とともに社会経済システムも価値観も新旧がぶつかり、変容しようとしている。 この勉強会は、こうした社会経済システムの変容の中で重要なテーマであるエネルギーを中心に、その転換期において企業が直面するジレンマに対して、各社・各人の異なる視点を持ち寄り、これから生き残っていくためにどのように対処していけばよいのか、社会に生きるひとりとして議論する“緩やか”な場を、オムロン フィールドエンジニアリング株式会社、関西電力株式会社、株式会社meguriが企画し、企業を超えた有志で不定期に開催している。
西日本カーボン貯留調査株式会社代表取締役社長。1994年3月慶應義塾大学理工学部応用化学科卒。1994年4 月日本石油(現ENEOS)に入社。リテール販売から石油探鉱まで、石油事業の上流から下流まで広範な事業に従事。エネルギー業界に職を得たことで、エネルギーと人類社会の関係に興味を持つようになる。以来サラリーマン生活を続けながら、なぜ人類はエネルギーを大量に消費するのか、そもそもエネルギーとは何なのかについて考えることをライフワークとしている。2021年にその思索の集大成として、『エネルギーをめぐる旅~文明の歴史と私たちの未来~』(英治出版)を著した。趣味は、読書、料理、そしてランニング
「エネルギー問題」を学び、対話を通じて私たちの未来を考える
今回のエネルギー勉強会は、OMRON東京事業所の一室にて実施。会場には勉強会を主催する3社やその関連会社を中心に、40名以上が参加しました。
冒頭、オムロン フィールドエンジニアリング株式会社執行役員の榎並顕氏は、オムロン創業者・立石一真氏が提唱した「SINIC理論」に触れながら、エネルギー勉強会の意義について説明しました。
「オムロンは創業者・立石一真の『SINIC理論』を経営の羅針盤としています。この理論では現代を大きな転換期と捉えており、大量生産・大量消費型の社会から持続可能な社会への移行期にあたると考えられています。
社会・経済システムへの転換の過程において、新旧の価値観や産業構造が混在するなか、さまざまな課題が顕在化してきました。特にエネルギー業界は、多様な産業が複雑に関わる分野であり、大きな構造変革の時期を迎えています。
私たちエネルギー事業者も、この変化に対応してビジネスモデルの見直しを迫られているのです。そこで、異なる経験や視点を持つ方々と未来について語り合うコミュニティとして、この勉強会を続けてきました」
今回の勉強会は、エネルギー問題の専門家による講義を受け、前提となる歴史やエネルギー問題の現状を参加者全員が学んだうえで、私たちの未来について考える対話に繋げたいという意図でプログラムが組まれました。
“自分の頭で考える姿勢”を持つことから、エネルギー問題を考えることが始まる

早速、エネルギー問題に関する講演がスタートしました。講師を務めていただいたのは、「エネルギーをめぐる旅―文明の歴史と私たちの未来」の著者である古舘恒介氏です。
古舘氏は日本石油(現ENEOS)にて石油事業の上流から下流まで幅広い事業に従事した経験から、エネルギーと人類社会の関係に興味を持つようになり、現在に至るまで「なぜ人類はエネルギーを大量に消費するのか」「そもそもエネルギーと何なのか」について独自に研究を重ねてきました。
そんな古舘氏による、今回の講演のタイトルは「エネルギー問題を考えるということ」。講演の冒頭で古舘氏は、エネルギー問題について考えるとき、まず「自分の頭で考えることが重要だ」と強調しました。
古舘氏「世の中にはさまざまなイデオロギー(人間の行動を左右する根本的な物の考え方の体系)が存在しています。
社会にはびこるイデオロギーに簡単に左右されないためには、まず自分の頭で考えて答えを出すことが重要です。自分の頭で考えなければ、意見に重みが出ず、責任を取ることもできません。」
また、エネルギー問題をはじめとする社会問題は、複数の問題が複雑に絡まりあっており、1つの問題に対して1つの解決策では太刀打ちできないのが現状です。
さまざまな考え方があるなかで、一面的なイデオロギー的議論に流されないためには、問題が複雑であることを念頭に置くことが必要だと古舘氏はいいます。
そのためには問題が起きた本質的な理由を歴史から学び、取り入れた情報を精査し、思考を巡らせなければならない。
「まずは考える姿勢を持つこと。そこからエネルギー問題を考えることがスタートします。」と古舘氏は語りました
エネルギー問題は、生半可な知識と正義では太刀打ちできない


続いて、エネルギー問題を考えるうえで、まず理解しておくべき2つの観点について、古舘氏から共有がありました。
まず1つ目は、エネルギー問題の抱える「複雑さ」の理由についてです。エネルギー問題は多くの場合「気候変動」だと捉えられがちですが、それほど単純なものではありません。
前述した通り、エネルギー問題は複数の問題が重なりあっています。そして、それらすべてを理解するには膨大な知識が必要であることが、私たちがエネルギー問題に対して感じる複雑さの一因となっているのです。
では、エネルギー問題を構成する複数の問題と、働きかけるために必要な知識とは何なのでしょうか。古舘氏はエネルギー問題の構造を大きく分けて3つに分解することで、それぞれに必要な背景知識について説明してくれました。
まず第1層が「資源分配問題」。これが人類社会を形成するうえで最初に起こったエネルギー問題です。
人類が獲物や収穫物をどのように分配し、人口を増やし、社会を形成してきたのかを理解するためには、社会学や政治学、宗教などの知識が必要です。
次に第2層が「地域レベル環境問題・資源枯渇・資源偏在」。人類にとって重要なエネルギー源である森林資源の活用やそのコントロール、近代社会以降においては化石燃料やウランの利用などは、エネルギー問題を語るうえで欠かせない要素です。
これらを理解するには、農学や理学、工学、さらには経済や政治についての理解も重要になります。
最後に第3層が「地球レベル気候変動問題」です。エネルギー問題の代表格と捉えられている気候変動は、温室効果ガスやそれを生む現代社会の構造などから生まれており、一から理解するためには理学や政治学、経済学を学ばなければなりません。
このように、エネルギー問題と一口に言っても、詳しく理解するためには幅広い分野での網羅的な知識(リベラルアーツ)が必要なのです。
「エネルギー問題とは、社会そのものの問題です。生半可な知識では太刀打ちができない非常に複雑な問題であることを念頭に置いておいてほしいですね」と古舘氏は語りました。
ここまでの講義の内容を聞くと、エネルギー問題とは複雑な問題であり、個々人では到底解決できないように感じるかもしれません。
しかし、古舘氏は経済活動や社会システムの問題だと考えられるエネルギー問題こそ、人々の「心」が重要だと参加者へ語りかけました。ではなぜ「心」の問題なのでしょうか。エネルギーの歴史を紐解き、現代社会の構造を知ることでそのヒントを見つけられるはずです。
人類史における5つの「エネルギー革命」とは?

古舘氏は、エネルギー問題を理解するうえで重要な、人類の歴史における5つの「エネルギー革命」について、それぞれの社会的意義とともに解説をしました。
エネルギー革命とは、現在使用されているエネルギー資源がほかの資源へと急激に変化することを指します。
まず、人類を人類たらしめた第1の革命は「火の利用」。約200万年前、他の生物が恐れる火を、私たちの祖先は積極的に使い始めたのです。
火を使った調理により、人類は消化効率を高め、余剰エネルギーを脳の発達に回すことができました。「現代でも、私たちの体は火を使った調理を前提とした構造になっている」と古舘氏は指摘します。
次なる革命は、約1万年前の「農耕の開始」でした。それまでの人類は、地表に降りそそぐ太陽エネルギーを他の生物と奪い合って暮らしていました。
しかし、土地を開墾し田畑を整備する際、人類は農作物の生育を妨げる植物を意図的に取り除き、代わりに食料として利用できる作物を植えることで、その土地の太陽エネルギーを人類が占有できるようになったのです。
この革命によって、人類は安定的な余剰の食料を確保できるようになり、人口はみるみる間に増加。さらに食料確保以外にも手工業へ人的エネルギーを割けるようになり、文明発展の礎となりました。
18世紀に入ると、「蒸気機関の発明」という第3の革命が起きます。ジェームス・ワットによって改良された蒸気機関は、熱エネルギーを運動エネルギーに変換する画期的な技術でした。熱源さえあれば無尽蔵に近いエネルギーが使えるようになったわけです。
19世紀の「電気の利用」は、第4のエネルギー革命でした。発電機とモーターの発明により、人類は取り出したエネルギーを電気に変換して移送し、別の場所でまた必要なエネルギー形態へと変換して使うことができるようになります。
これまでのエネルギー形態にはなかった、生成する場所と使用する場所が離れていてもよいという特性により、電気は人類にとって扱いやすいエネルギーとして不動の地位を獲得することになります。これは、現代の電化社会を築く決定的な一歩となりました。
そして20世紀、「人工肥料の開発」という第5の革命が訪れます。
作物の生育には窒素が不可欠ですが、土壌中の窒素は作物の栽培によって徐々に失われていきます。また自然界では、雷や土壌微生物の働きによって大気中の窒素が土壌に取り込まれますが、その量は限られており、これが食料増産の壁となっていたのです。
そんな課題を解決したのが、空気中の窒素を人工的に固定する「ハーバー・ボッシュ法」の開発でした。この方法では、高温・高圧の条件下で大量のエネルギーを投入し、大気中の窒素を化学的に固定します。莫大なエネルギーを必要とする技術ではありましたが、これにより大量の化学肥料生産が可能となり、食料生産量は飛躍的に増加。
かつて予測された、人口増加の限界を超える道が開かれたのです。現在、世界の総エネルギー消費量の2〜3%が人工肥料の製造に使われているという事実は、その重要性を物語っています。
勉強会前半の結びに、古舘氏は次のように語りました。「これらのエネルギー革命は、人類に比類なき豊かさをもたらしました。しかし、私たちは自然界がもつ制約から解放された一方で、際限のないエネルギー消費へと突き進んでいったのです」。
5つのエネルギー革命によって、莫大なエネルギーを手にすることとなった人類社会は、その後、どのように変化していったのでしょうか。
後編では、産業革命以降の人類社会の構造と、現代のエネルギー消費に対して警鐘を鳴らす古舘氏の見解、そして講演後に行われたワークショップの様子をレポートします。