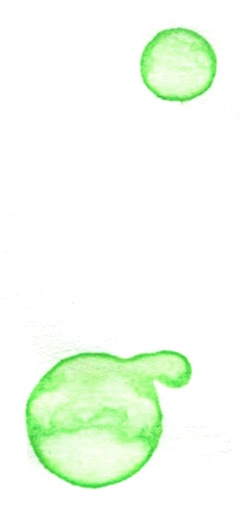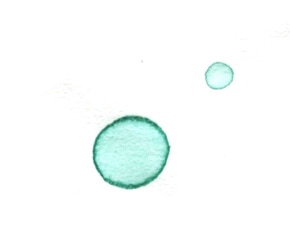Journal

こちらの記事はCQ note記事の原文転載となります
元記事:「無限に成長できる」幻想からの脱却へ。「エネルギーをめぐる旅」著者・古舘恒介が問いかける、これからの時代の”ゆたかさ”【勉強会レポート】
勉強会レポート前編では、「エネルギーをめぐる旅」著者・古舘恒介氏から、エネルギー問題の複雑さと、人類がエネルギー革命を重ねて発展してきた歴史について学びました。
後編では、エネルギーの観点から、産業革命以降の社会がどのように成り立っているのか、そしてその構造がもたらす課題について、古舘氏の講演内容をお伝えします。
また講演後は、参加者一人ひとりが「エネルギー問題を解決するために必要なこと」「そのために私たちができること」という問いについて考える対話型のワークショップを実施。
異なる業種・立場から集まった参加者同士での意見交換を通じて、これからの時代における新しい豊かさのかたちを模索しました。
産業革命以降、莫大なエネルギー消費によって発展を遂げてきた私たちは今、どのような未来を目指すべきなのでしょうか。
テクノロジーの進化、人々の考え方や生き方、価値観の変化、温暖化をはじめとする様々な社会課題など、時代の変化とともに社会経済システムも価値観も新旧がぶつかり、変容しようとしている。 この勉強会は、こうした社会経済システムの変容の中で重要なテーマであるエネルギーを中心に、その転換期において企業が直面するジレンマに対して、各社・各人の異なる視点を持ち寄り、これから生き残っていくためにどのように対処していけばよいのか、社会に生きるひとりとして議論する“緩やか”な場を、オムロン フィールドエンジニアリング株式会社、関西電力株式会社、株式会社meguriが企画し、企業を超えた有志で不定期に開催している。
西日本カーボン貯留調査株式会社代表取締役社長。1994年3月慶應義塾大学理工学部応用化学科卒。1994年4 月日本石油(現ENEOS)に入社。リテール販売から石油探鉱まで、石油事業の上流から下流まで広範な事業に従事。エネルギー業界に職を得たことで、エネルギーと人類社会の関係に興味を持つようになる。以来サラリーマン生活を続けながら、なぜ人類はエネルギーを大量に消費するのか、そもそもエネルギーとは何なのかについて考えることをライフワークとしている。2021年にその思索の集大成として、『エネルギーをめぐる旅~文明の歴史と私たちの未来~』(英治出版)を著した。趣味は、読書、料理、そしてランニング
産業革命以降の人類が信じてきた「マネー」の脆さとは

歴史を見れば明らかなように、産業革命以降の人類社会は大きな変貌を遂げました。その姿について古舘氏は「巨大な台風のようなもの」と表現しました。
台風が強大なエネルギーを受けつづけることで形を保っているように、現代社会もまた莫大なエネルギー供給によって成り立っているというのです。
古舘氏は物理学の用語を借りて、これを「散逸構造」と言い表します。エネルギーの流れがあるなかで、渦を巻きながら一定の形を保ち続ける構造体。それが現代社会の姿なのです。しかし、問題はこの構造は決して強固なものではないということだと古舘氏は指摘しました。
古舘氏「社会の発展は、エネルギー供給量が右肩上がりで増えつづけられたから実現できただけ。もしエネルギー供給が細れば、台風が衰えるように、社会構造も一気に崩壊しかねないのです。
さらに深刻なのは、私たちが『永遠の成長』という幻想を追いつづけていること。資源が有限である以上、資本主義社会が前提とする無限の成長は、物理的に不可能なのです」
さらに古舘氏は、「産業革命を境に社会の在り方が根本的に変化したことにも注目してほしい」と語りました。
産業革命以前の社会では、太陽光エネルギーの効率的な利用が権力の基盤となり、土地を基礎とした封建制(土地を媒介とした支配や従属関係に基づく社会システム)が成立していました。
一方、現代社会ではすべての価値が「マネー」によって規定されています。あらゆるものが経済的価値や金銭的価値によって測られる世界なのです。しかし、「マネーの信用を担保しているのは、実は莫大なエネルギー供給だ」と古舘氏はいいます。
マネーの信用は決して抽象的な約束事だけで成り立っているわけではなく、私たちが商品やサービスを生産し、流通させ、消費する。その経済活動のすべてに、大量のエネルギーが必要とされているのです。
だからこそ、私たちが絶対的な価値と信じる「マネー」も、実は予想以上に脆い基盤の上に成り立っているのかもしれません。現代社会は「資本の神(マネーへの信奉)」を信仰する一方で、その神を支えるエネルギーという現実から目を背けてきたともいえるでしょう。
エネルギー革命で起こったのは「時間の早回し」

「5つのエネルギー革命で実現してきたのは、つまるところ『時間の早回し』です」と古舘氏は続けます。
火による調理は消化の時間を短縮し、農耕は食料確保の時間を効率化しました。産業革命以降は、蒸気機関によって移動や生産の時間を圧縮し、電気の活用であらゆる作業の時短を実現。さらに人工肥料は、作物の生育時間さえも短縮することを可能にしました。
しかし、前述したようにこのような時間の早回しは「右肩上がりの成長」を信じて行われるエネルギーの大量消費によって支えられており、持続可能とはいえません。
古舘氏は「私たちは、時間を早回しにすることを求めつづける現代社会のあり方そのものに、問いを立てる必要があるのではないでしょうか」と訴えます。
持続可能な社会を実現するためには、エネルギー需要の抑制が不可欠です。しかし、その議論は単なる技術的な省エネルギーの話に留まるべきではありません。
むしろ、私たちは「時間を早回しにすることを求めつづける」という、現代社会の価値観そのものに向き合う必要があるのではないか。それが古舘氏がエネルギー問題を通じて、私たちに投げかけたい問いなのです。
エネルギー消費の在り方に向き合い、どう生きるべきかを考え直す


エネルギー革命によって加速してきた「時間の早回し」。では、私たちはどのような社会を目指すべきなのでしょうか。古舘氏はその答えに繋がる気候変動問題の本質について解説しました。
古舘氏「気候変動問題の本質の1つとして、土地が足りなくなっていることが挙げられます。人口は今なお増え続け、食料生産にも莫大なエネルギーが必要とされる。このとき、大量の土地を必要とするエネルギー密度(※)の低い再生可能エネルギーに頼るだけでは、究極の解決策とはなりえない」
※エネルギー密度とは、単位面積あたりでどのくらいのエネルギー量を発電できるかを表す値。再生可能エネルギー(太陽光発電や風力発電など)はエネルギー密度が低く、多くの電気を作るために、広大な土地が必要となる。
核融合などの新技術に期待を寄せつつも、その実現には少なくとも今世紀〜来世紀初頭までの時間がかかるというのが古舘氏の見解だといいます。
結局のところ、持続可能な社会を実現するには、今もなお続く人口増加のなかで、いかにエネルギー消費量を抑えられるかが鍵になります。しかし、永遠の成長を追いつづけ、時間の早回しを求める既存の価値観の延長線上では、エネルギー消費量を抑えることは難しい。
だからこそ、ただ代替手段として再生可能エネルギーを導入すればよいと単純に考えるのではなく、既存の社会を見つめ直し、再生可能エネルギーを運用できるような自然と調和した社会の在り方を考える努力をすることが重要なのです。
再生可能エネルギーは究極の解決策にはならなくとも、そうすることで社会の在り方がシフトするきっかけとなり得ます。
古舘氏「社会の在り方を問うというのは、つまり人々の「生き方」ひいては「心」の在り方を問うということです」
冒頭でエネルギー問題において人々の「心」が重要だと示した古舘氏は、その心の問題として、私たちの生き方を見つめ直す日が来ているのだと、参加者に問いかけました。
エネルギー問題に向き合うための基本的な姿勢、考えるために必要な歴史や知識の材料、私たちが気がついていない現代社会が抱える課題、そして最後に持続可能な未来を残すためのヒントを語り、古舘氏の講演が終了しました。
講義をもとに「エネルギー問題」について考える対話型ワークショップを実施

講義終了後、参加者全員で「エネルギー問題」について考える対話型ワークショップを実施しました。「ワールドカフェ」と呼ばれる手法を用いて、3〜4人1組でテーブルを囲んで対話を始めます。
まず1回目の対話では、古舘氏の講義を受けての感想や、「エネルギー問題を解決するために必要なことは?」「そのために私たちができることは?」という問いについて、活発な意見交換が行われました。
各テーブルでは、参加者それぞれの視点からアイデアが出され、そこからさらに新しいアイデアが生まれ、対話が深まっていきます。

続く2回目の対話では、各テーブルに1名のホストを残し、他のメンバーは別のテーブルへと移動。新しいメンバーとの対話を通じて、視点がさらに広がります。
最後に元のテーブルに戻り、移動先での気づきや発見を共有しながら、問いへの理解を深めていきました。

勉強会の最後に、参加者数名から感想を発表してもらいました。その一部を抜粋してご紹介します。
エネルギーの地産地消に関心を持つ参加者は、「大規模集中型から地域分散型のエネルギーシステムへの転換が、これからの社会づくりの起点になるのではないでしょうか。自然と調和した社会を作るためには、再生可能エネルギーの特性を活かした地域づくりや、エネルギーの地産地消の仕組みづくりなど、具体的なアクションを起こしていく必要があります」と語りました。
また、別の参加者からは「私たちはまず『幸せ』について考え直す必要があると感じました。エネルギー革命は常に時間の短縮を追求してきたことがわかりましたが、エネルギー大量消費社会に生きている我々だからこそ、本当の豊かさや幸せについて立ち返らなければ、ただ流されていってしまうのではないでしょうか」という意見が。
さらに、企業からの参加者は「エネルギー問題を解決するような企業側のムーブメントを作っていく必要があります。企業が率先して変化することで、消費者の行動も変えることができるのではないでしょうか。そのために、私たち企業は具体的にどのようなアクションを起こせるのか、考えていかなければなりません」と、ビジネスの視点からの提案もありました。
このように、それぞれの立場から異なる気づきが示される一方で、エネルギー問題の解決には社会全体での取り組みが必要だという共通認識が生まれていました。
古舘氏の講義で示された歴史的な視点や、対話を通じて得られたさまざまな気づきは、参加者一人ひとりにとって、これからの行動につながるヒントとなったようです。
まずは今の社会を「肯定する」ことから始めよう

約4時間にわたって行われた勉強会は、参加者のみなさんがエネルギー問題について理解を深め、さらに目指すべき未来について考えるための貴重な機会となりました。
エネルギーにおける人類史を振り返ってみると、人間の持つ成長への貪欲さを知るとともに、持続可能な未来について考えを巡らせない愚かさを感じて、暗澹たる気持ちになる方も少なくないかもしれません。
しかし、古舘氏が講演の結びに強調していたのは「未来へ希望を持つ」ことの重要性でした。
人類はその類まれなる優秀な頭脳の力によって、目の前に未来というものがあることを知り、さらに未来を自らの力で作り変えていくことができると気が付きました。
だからこそ、過去の経験と知識を活かして将来を俯瞰し、計画的に行動ができるようになったのです。その「先見の明」こそが人類の持つ力なのだと古舘氏はいいます。
産業革命以降の異常なエネルギー消費は大きな課題です。しかし、それ以前の生活に戻ることは難しい。
ならば、まずは「現代社会を肯定することから始めよう」と古舘氏は語ります。歴史を学び、私たちが思った以上に把握できていない現状を理解したうえで、少しずつ新しい社会の在り方にシフトしていくことが求められているのです。
とはいえ、新しい社会へのシフトには、決して大きなことが求められているわけではありません。
例えば、日常生活でもできるような「ゴミの分別」や「プラスチックの削減」といった小さな行動も重要な一歩となるでしょう。
また、「コストパフォーマンス」や「タイムパフォーマンス」といったような時間の早回しに囚われるのではなく、そういった社会の在り方から「積極的に降りる」という心の持ちようも必要とされています。
人類が持っている「未来を想像し、考える力」という強みを最大限に活かし、小さな努力を積み重ね、希望を持ちながら新しい社会へと変化する姿勢を持つ。
地道に見えるかもしれませんが、小さな努力が新たな未来を生み出すことを、まずは信じてみるところから始めてみませんか。